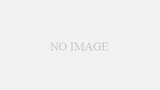けがをしたり、かぜをひいたりしてクリニックや診療所などを受診した場合、必要があれば薬をもらい、多くの場合は数日で元通り、元気になります。 こういう場合、たいていは医師の診察のみで、あるいは必要に応じて血液検査やレントゲン、超音波、CT, MRIなどの画像検査(画像診断)を受け、総合判断します。そこには病理は登場しません。
生検、からだから、ほんの少し“情報”をとってくる
たとえば、「ダイエット中じゃないのに体重が減った」「便に血が混じった」「からだにしこり(腫れ物)がある」——そんなとき。医師は様々な検査をして、その原因をある程度予測します。ついで、「おそらくこれが原因だ」というものから、ほんの少しの“かけら”を取ってきて(生検といいます)、病理のもとに届けられ、それを詳しく調べることがあります(見立ての良い医師は、「これこれの病気だと思います」とか「あの病気を疑っています」とか、「あの病気で間違いないです、確認お願いします」とか、かなりの確度で当ててきます)。
このとき調べるのは、「数字」ではなく「見た目」です。 細胞や組織(組織は細胞の集まり)の、形・並び方・色合いなど。 その“かけら”がどんな様子をしているかを見ることで、 病気かどうか、病気ならどんな病気かを判断します。病気の正体がわかれば、治療という次のステップに進むことができます。場合によっては、病気でもまだ治療が必要でない、そんな状況もあり得るかもしれません。
※最近は「見た目」にも一歩踏み込んでいます。細胞を構成する特定のたんぱく質(免疫組織化学という抗原抗体反応を利用する)の有無あるいは分布をみたりするのは日常のことで、遺伝子の変化もみたりすることも日常になりました、なりつつあります、なってきています。病気の細胞が持つ特定のたんぱく質の有り無しや、特定の遺伝子の変化の有り無しで、病気の名前を付けたりすることも増えてきました。それはつまり、特定のたんぱく質の有り無しや、特定の遺伝子の変化の有り無しで治療が異なったりするので、特別に分類する必要性が出てきたからですね。
目立たない場所で、医療に深く関わっている
病理は、医療の現場では表に出てくることはとても少ないです。患者さんの前に登場することは稀です。 診察室にはいませんし、手術室にも普段はいません。(今の勤務先ではやっていませんが、「病理外来」という、病理医が患者さんと話す機会は少ないながらもあります)。
生検という病気の一部をつまんできたり、あるいは手術で取り出された病変が病理のもとに届けられます。それを調べ、 生検であれば病気がどんなものかを診断します。それにより手術が必要か、あるいは薬を使った治療をするのが望ましいかなどを判断する材料になります。手術であれば、そのまえに生検をして病気の名前が決まっていればその確認や、病気の広がり(局所にとどまっているのか、手術で病気は取り切れているのかなど)などをあらためて確認します。その情報を踏まえ、手術後にさらに治療が必要なのか、あるいは経過を見ていくのがよいのか、などを判断します。つまり、腫瘍の診断について、病理は大きな役割を担っています。
影の存在である病理もまたチーム医療
病理という仕事は、病理医だけでできるものではありません。
・臨床検査技師(りんしょうけんさぎし)
病理診断に必要な標本を作る専門家(国家資格)です。 標本を作るためには、とても多くのプロセスを経る必要があります。まずは検体をホルマリンに入れたんぱく質を「固定」します。その後、検体をパラフィンというろうそくのようなものに入れ固めて薄く切るのですが、ホルマリンは水溶性で、パラフィンは脂溶性です。そのままでは水と油でなじみませんので、なんとかします。
まずはエタノールにいれて水をアルコールに置き換えていきます(脱水)。その後キシレンという有機溶剤に入れ脂溶性を高めていきます(透徹)。その後検体をパラフィンに入れ冷やし固めます(包埋)。そうすることで、次のステップの薄切(はくせつ、文字通り薄く切ること)にすすめます。通常の標本は、組織を3 μm(1000分の3 mm!)の厚さに薄く切ったあと、様々な方法で染色します。基本の染色はヘマトキシリン・エオジン染色といいます。ほかにも、特定の構造物を見やすくするための特殊染色や、特定のたんぱく質や遺伝子の変化を可視化する技術もあります。病理診断は、臨床検査技師の技術がなければ成り立ちません。「医療を支える病理診断」を支える臨床検査技師ですね。
なお、固定までは検体を提出した医者の仕事、脱水透徹は機械がやってくれます。その後の包埋と薄切はひとの手によるところが多いと思います。米粒よりも小さな検体は、とても慎重に行う必要があります。
なお、臨床検査技師は病理のみにかかわるものではありません。施設によっては病理専従の技師もいれば、病理を兼務している技師もいます。臨床検査には病理だけでなく、生理検査(心電図、呼吸機能、脳波、超音波など)や生化学、血液、免疫、微生物、輸血など多くの部門があります。
・細胞検査士(さいぼうけんさし)
臨床検査技師のうち、細胞を見る「プロ」がもつ資格です。顕微鏡で一個一個の細胞を観察して、「あやしいものがないか」を見つけ出す専門家です。かけらを一部つまむことを生検、生検や手術検体の病理診断を組織診断といいますが、細胞一個一個をみて診断することを「細胞診断」といいます。細胞診断は、つまむことが難しい検体の診断に威力を発揮します。たとえば尿などからだにある液体中にも細胞は浮遊しています。あとは病変表面をこすることで細胞をこそぎ取ってきて、それを観察することもできます。もしくはものすごく細い針を刺して吸引することで細胞を病変から「吸い取って」きます。
なので、細胞診は、つまんでくる生検よりも痛みが少ないことが多いのが特徴といえます。また、病理における診断の順番は、細胞診→生検→手術の順になることが一般的です。なので、細胞診はスクリーニング(病気かどうかの第一関門)みたいな扱いを受けることが多いと思います。が、臓器によっては細胞診がものすごく威力を発揮して、生検をすっ飛ばして細胞診→手術になる臓器もあります。甲状腺が有名かと思われます。
・病理医(びょうりい)
医療における病理医は、病理診断科で働く病理診断医です。大きな手術検体は、病理医が観察して病変部から過不足のないよう切り分け(切り出しといいます)、臨床検査技師に標本を作ってもらい、病理診断をします。細胞診標本は、細胞検査士が細胞診断したものを、確認します。そのような診断をするのが病理医です。病理医のした診断は、検体を提出してくれた依頼医(あなたから検体を取ったお医者さん)に届けられ、今後の診療に役立てられます。
病理診断は依頼があってこそ
このように、病理はチームの総力戦です。 どれかが欠けても、より確からしい診断にはたどりつけません。
腫瘍の診断には、病理医が大きな役割を担うのはもちろんですが、病理医に検体を届けてくれるのは患者さんを見ているお医者さんです。ここが怪しい、こういう病気じゃないか?と考えて検体を採取してくれる医者(内科医も、外科医も、はたまた放射線科医も採取します)がいなければ、病理診断は始まりません。