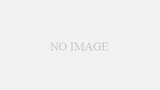病気の成り立ちを探るということ
病気の成り立ちを研究するのが病理学です。病気の原因やその仕組みを解明するのが目的で、病気がどのようにして起こり、それがからだにどのような変化を及ぼすのかを探求します。
病気を「診断する」から「なぜそうなるのか」へ
医療における病理において、タンパク質の変化や遺伝子の変化を調べ診断や治療に役立てると書きました。それは、特定の病気が、タンパク質にコレコレの変化が起きている、とか、特定の遺伝子にコレコレの変化が起きている、ということが研究によって明らかになったから、診断に応用されるようになったのです。これは診断に役立った例ですが、、病気の原因や仕組みを知ることが、新しい治療や、はたまた予防につながることもあります。病気にまつわる「なぜ、なに」をより根本から理解できれば、「どうすればその病気を早く見つけられるか、あるいは防げるか」「どう治療すれば治るか」といった対策が見えてきます。
病理診断との違いとつながり
病理診断は、患者さんから採った組織や細胞を調べて病名を確定する医療行為です。一方、研究は、診断に用いる組織を使ってさらに深く病気の原因や経過を調べたり、実験で病気のモデルを作って検証したりする活動です。診断をしていると「わからないこと」にぶつかります。診断の延長に研究があることもあるし、研究でわかったことが診断に還元されることもあります。診断オンリー、あるいは研究オンリーの先生もいると思いますが、多くは診断医と研究者の両方の顔を持ち、診療しながら研究を進めています。自分が経験した症例を世に報告する「症例報告」も、立派な研究活動の一つだと思います(自戒も込めて)。
病理における研究の手法(の一部)
1. 病理診断目的に提出された検体を用いる
生検や手術で採取した検体を使うのは、自分の目で(肉眼で)、顕微鏡で病変を間近にみている病理医ならではです。標本で研究もできますし、標本になる前の検体を使うこともできます。形態(見た目)での研究もまだまだありますし、特定のタンパク質の有無や局在(どこにあるか)、遺伝子の変化なども、検体をつかってできる研究です。
2. 培養細胞を使う
たとえばひとのがん細胞を使って、シャーレで育て(培養して)特定の薬物にさらし、それが抗がん剤として治療に使えそうかどうか、あるいはどのようなメカニズムで作用しているのか、なぜ効かなくなってくるのか(耐性)などなどがあると思います。培養細胞の使い方にも、どのような細胞を使うか(たとえば正常の細胞、がん細胞)や種類(一種類だけ、複数種類を混ぜる(その比率は?))、どのような環境で培養するか(「地面」に接着させる、浮遊させる)など様々です。
3. 実験動物を使う
マウスなどの動物を使って、実験します。医学生のときに少し経験したきりですのであまり書けませんが、培養細胞を使った実験よりも、ひとの生体内の環境に近い状況を見ている、と考えることができると思います。
それぞれの強み
これら3つのうち1つだけを用いて、何かを明らかにすることもあります。とても素晴らしいことだと思います。それでも、たとえば培養細胞で明らかになった事象をひとの検体でも確認した、とかマウスでも再現できた、となるとより確からしいとか説得力が増してくると思います。たくさん実験をすると、それに比例してたくさんお金がかかるのですが。。。それに、培養細胞で再現性のある結果が得られたとしても、ひとや動物で同様の事象が確認できないことはままあります。手法ごとに特徴(得意不得意)があるので、仮説にあわせてどの手法を用いるのか、が大事なときもあります。僕自身は診断に偏っているのであまり書けませんが。
病理とデジタル、AI
ぼくにとっては動物実験よりも更に馴染みが薄いです。デジタル病理は、作製した標本をスキャナーでデータにします。まずそれ自体で、標本を持ち歩かなくても、顕微鏡がなくても、ネットとパソコンさえあれば病理診断ができるようになります。ここまではぼくも日常的にやっています。さらに、データ化したものをAIに学習させ、診断精度を上げようとしたり、新しい疾患概念を作り出したり、様々なことに利活用が進んでいます。
病の理を、少しずつ明らかにしていく
これらの手法を使って、がんや免疫、炎症、老化など様々な分野の研究に取り組み、病の理について挑んでいると言えるでしょう。研究成果が医療に還元され、またあらたな謎が生まれ研究が進んでいきます。医療と医学は絡まり合っていますね。